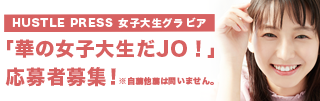舞台裏のプロフェッショナル
劇団た組。演出・脚本 加藤拓也
PHOTO=古賀良郎 INTERVIEW=斉藤貴志
中山絵梨奈さんは大人っぽくて
秋月成美さんは透明感がいいなと
――劇団た組。で6月に「いなくなれ、群青」、7月に「惡の華」と2ヵ月続けて公演。精力的ですね。
「8月、9・10月をまたぐ1本、11月とあって、来年4月にチェッカーズの『ジュリアに傷心』の舞台化もしますけど、12月にもう1本やる話も出ていて。それが決まると、半年間ずっとやりっぱなしの形になります」。
――22歳の若さがあってこそかもですね。「いなくなれ、群青」と「惡の華」はどちらも思春期の精神的な彷徨を描いた作品ですが。
「時期的に続いたのはたまたまですけど、『惡の華』に関しては『そもそも劇って何だろう?』とずーっと考えていたのを、春日たちのいう“向こう側”への衝動に重ね合わせました」。
――根源的な自問自答?
「劇って意味がわからないんです。ビジネス的観点から言うと、すごく非効率、非生産的でコスパが悪いじゃないですか。もちろん好きだからやってますけど、『これをやることによって何が生まれるんだろう?』と考えてしまうことは常にあって。そこから、この作品を舞台化したいなと思いました」。
――キャスティング的には、問題児の仲村役が特にポイントだったかと思いますが。
「そうですね。どうしようかと思っていたら、たまたま知り合いのプロダクションのマネージャーから『こういう子が入った』と言われたのが花奈澪さん。会ったら仲村に超そっくりで、すぐお願いしました」。
――宝塚出身で演技力には不安のないところで。優等生の佐伯役を初舞台の秋月成美さんにしたのは?
「こっちもずっと探していて、秋月さんは透明感があっていいなと思いました。本人がわりと周りからの見られ方に自分を合わせて行動してしまうところが、佐伯っぽいというのもあって」。
――佐伯の親友の木下役はGEMの森岡悠さんで、演技自体もほぼ初めて。iDOL Streetから推薦があったそうですが。
「基本的に僕は全員と会わせていただきます。あの役は仕切りたがりで、男からは嫌われがちなので、森岡さんみたいに誰にも受け入れられやすい人で見せるのもいいかなと」。
――昨年12月の「博士の愛した数式」では、SUPER☆GiRLSの宮﨑理奈さんが少年役を演じました。
「宮﨑さんは声が少年っぽいし、舞台メイクをしたら顔も少年に見えたので、『何とか』とお願いしたら、『いいよ』と言ってもらえました」。
――「いなくなれ、群青」のほうは、原作の小説が独特なタッチですね。
「遠回しな言い方だったり、比喩が多かったり。テーマ的な部分を大事にしながら台詞の構成を組み替えて、どこを立たせるかガッツリ考えて台本を書きました。原作をいい意味で崩しながら、劇としてブラッシュアップさせて。原作を読んだ方にこそ観ていただきたいです」。
――こちらでヒロインの真辺由宇役に中山絵梨奈さんを起用したのは?
「小説の絵と雰囲気が似てますよね。あとは身長。あれぐらい(167㎝)ある方はそんなにいないので。年のわりに大人っぽく見えるところも魅力的だと思います」。
――演出で“加藤流”というと、どんなところに出ますか?
「たとえば『泣け』『泣くシーンだ。悲しいんだ』と言ったら役者さんは、なんとか無理にでも泣こうとするじゃないですか。それは違うなと思っていて。感情が絞り出されるんじゃなくて溢れ出るための理由があるわけじゃないですか。その導線を僕は言ってあげるだけ。例でいうと『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』のとき、主人公が母親を亡くして、台本に空白の時間があって、そこで何をすればいいか? 『○○のことを考えてください。○○が目に入って、こういう場所でどんなものが想像できますか』と言った結果、涙が出て眠るという行動に至ったんです。僕として最初からそうして欲しかったのを、直接言わずに導線を与えました。本物の感情が生まれることを大事にしたくて」。
――ご自身も演技経験はあるんですか?
「遊びでコントをみんなでやるぐらいです。台本とか書かず、設定だけ付けてバンとやる。面白いことが最優先で、どういうくだりがあるのか、自分が入ってボケてツッコんでもらって……、というのはありますけど」。
――演じる側から演出に回ったわけではなく。
「役者として出たこともありますけど、そこを目指していたわけではないです。僕にとって演劇は、あくまで何かを表現するツール。演劇を作るときに自分のやることに付いた肩書きが“演出”だった……、という感じですかね」。
同世代のAKB48がグーンと来て
「負けない!」と奮い立ちました
――もともと17歳のときに、ラジオ番組のプロデュースから仕事を始めたんですよね?
「企画をラジオ局に持ち込んだんですけど、最初は軽い衝動でした」。
――その後、18歳でイタリアに渡ってユニットのMV監督を務めた経緯は?
「たまたま知り合いのディレクターがイタリアにいて、MVの監督をやるように言われたんです。フィレンツェでヘリコプターから空撮をやらせてもらいました。イタリア人の操縦士がドアをバーンと開けて、ブランブランの状態で撮って、めっちゃ怖かったです。当時は大阪に住んでいて、安い便が羽田からしか出てなくて。フィレンツェから13時間かけて羽田に帰ってきて、さらに2時間新幹線に乗って大阪に帰るのが面倒くさくなって、そのままヌルッと東京に住んじゃったんです。しばらくはホームレスをやってました」。
――我が道を行く人生で(笑)。今回の2作だと、キャストと年齢が近いことは演出家としてアドバンテージになります?
「良し悪しですね。話し掛けやすさはあります。30・40代の役者さんが、一番距離感に気をつかいます。踏み込みすぎてもどうかと思うし、向こうもどう詰めてきたらいいかわからないだろうし。50・60代になると逆にもうフレンドリーに接してくれて、こっちもグイグイ行けるんですけど」。
――今後も若いキャストを使った公演は増えそうですか?
「60歳の方が主役の作品もやりますし、そこは幅広く。でも、今年はわりと学校ものが多いので」。
――キャスティングのために、日ごろから若い女性タレントにアンテナは張っているんですか?
「いろいろ観てます。特にCMと映画ですかね。あとはミュージックビデオ」。
――CMだと、15秒のなかにそのタレントの魅力が端的に現れているから?
「正直こういう作品って、ヴィジュアルは大事じゃないですか。第一印象で惹かれなかったら、観てもらえるのか。もちろん演技で支えてくれる人も必要ですけど、メインになる人はパッと見た印象も大きいので、CMで観るのはいいなと思います」。
――最近気になった人はいます?
「やっぱり桜井日奈子さんはすごいですよね。あと、木竜麻生さんという人がいて。今CMには出てないですけど、窪塚洋介さんにダメ元で当たったときに事務所のホームページを見ていたら、目につきました」。
――アイドルのライブも観に行きますか?
「原宿駅前パーティーズは一回行って、すごかったですね。特に岩崎春果さんが印象に残りました。普通にライブとして面白かったのがベビレ(ベイビーレイズJAPAN)。シンプルにカッコ良かったのが東京女子流」。
――けっこうご覧になっているんですね。
「ライブ照明が好きなんです。照明を見にライブに行くところもあって。派手なレーザーとか『カッコイイな』と思いつつ、演劇とは違うというのもあるし、お金もなくて(笑)、できなかったり。@JAMのメインステージのでんぱ組.incの照明なんか、カッコ良かったですね。VJと相まって」。
――そういう視点は演出家ならではで。
「森美術館の照明も『これか!』というのがありました。この前観に行って、『光の演出があります』みたいなことが書いてあって、『どんなのだろう?』と思いながら入ったら、『これは太陽だ!』という。直接太陽が作ってあるわけではないけど、すごいなーと思いました」。
――演出する舞台でも、照明は重視していたり?
「一番時間をかけるところです。劇場に入って場当たりとか仕込みの段階から、べったり付いて打ち合わせします。作品としての部分を優先しちゃうので、わざと影を作ったり役者さんの顔を見えなくするときもありますけど」。
――仕事と関係なく、好きだったアイドルはいますか?
「小学生のとき、常盤貴子さんが好きでした。窪塚さんとやっていた『ロング・ラブレター~漂流教室~』を観て。アイドルだと、仕事を本格的に始めた頃にAKB48がグーンとなって、応援したいとかでなく、悔しい気持ちを奮い立たされる感じでした。売れた頃のメンバーとほぼ同じ年代なんです」。
――前田敦子さんや高橋みなみさんたちの91年組より2歳下で、渡辺麻友さんと同い年ですよね。
「向こうはテレビに出て華やかだったから、闘志が沸いてきたというか。『負けないぞ』という気持ちが強かったです」。
――加藤さんも10代の頃からメディアで制作に関わっていた点では、秋元康先生を連想しますが。
「いや、全然そんな」。
――ご自分ではどういう存在を目指しているんですか?
「やりたいことはたくさんありますけど、『こうなりたい』みたいなものは正直ないですね。いろいろやっているうちに今に至る感じなので。ただ、良い面も悪い面も含め、今の僕にしかできない体制にはなっていると思います。『こういう風に見せたい』というところはあって」。
――若き演出家として、上の世代にない発想もたくさんあるでしょうし。
「どうなんですかね? レールのない道を行ってるとは思うので、独自に切り開いていきたいというのはあります。わざわざ他の方のやり方に合わせることはないし、しがらみでやりたくないので。HUSTLE PRESSさんのサイトを観ても、知らなかったけどいいなと思う人はいますし」。
――そうですよね。
「演出的にもカンパニーとしてのスキームも、他の劇団とは違うスタイルで来ているので、そこは貫き通したいです」。
加藤拓也(かとう・たくや)
生年月日:1993年12月26日
出身地:大阪府
【CHECK IT】
わをん企画代表。プロデューサー、演出家、脚本家。
17歳のときにFM局でラジオ番組のプロデュース、構成を始め、18歳のときに渡伊、AJ UnityMV監督を務める。帰国後、映像&宣伝企画プロダション「わをん企画」「劇団た組。」を立ち上げる。主宰する「劇団た組。」で「博士の愛した数式」「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」などの舞台を上演。第9回目公演「いなくなれ、群青」を6月22日(水)~26日(日)にLIVESTAGE hodgepodge(ほっぢポッヂ)、第10回目公演「惡の華」を7月27日(水)~31日(日)に浅草ゆめまち劇場にて開催。
詳しい情報は公式HPへ
加藤拓也 個人Twitter